


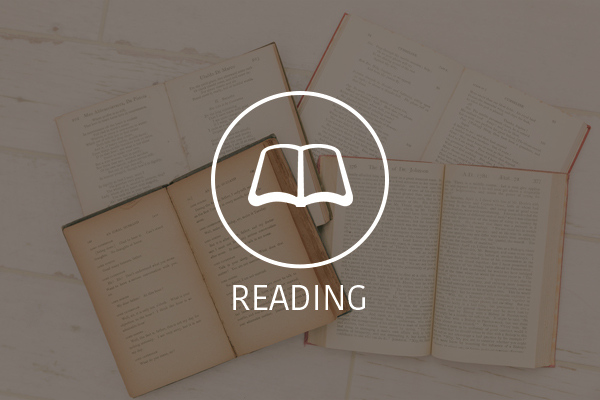
こんにちは。デザイナーのフジモトチエです。
皆さんは、最近読書していますか?
実を言うと私も、最近は以前よりも読書する時間が減ってしまっていたのです。そんな矢先、私の所属するデザイン研究課でも読書会を始めよう!という流れとなりました。
今回は、最近のデザイン研究課の取り組みのひとつ「読書会」についてお話ししたいと思います!
まずは読書会を開催する目的について。
「デザイン研究課で必要とされる共通知識や考え方について話し合い、理解を深める」
ということをひとつの目的として設定しています。
どんな本を読むかをピックアップしていき、指定図書を決定します。
そのあと約1ヶ月の期間を設け、各自決められた章までを読みこんでいきます。
そして事前に提示しておいたポイントを順番に話してもらい、他の人たちがそれに対する意見を交換していきます。
今回はこの3つのポイントに絞って読書をしてもらいました。
(1) 全体からもっとも印象に残った部分はどこか(章問わず、1~2程度)
(2)この本で明日から実践したいこと、またはすでに自分で実践していること
(3)他の人の感想に対する意見、雑感
(1)知識の偏りを知ることができた
日頃から自分でもデザインの情報収集を行っているのですが、
どうしても自分の興味のある分野の情報に偏りがちになってしまうことがあります。
自分が知らなかったデザインや事例など、各自が持っている情報を引き出しあいながら
議論することで、今まで聞いたことがあるだけだった事柄への興味が深まります。
私の場合は”靴下の商品開発にまつわるイメージ調査”の話題から興味を持ち、
商品企画やブランディングの成功事例について調べ始めました。
日頃の業務でもキャンペーンの企画を考える機会もあるので、
企画の作り方についてもっと理解を深めなければいけないなと感じました。
(2)デザインの学び方について考えることができた
独学で行っていたデザインの勉強方法について意見交換することができました。
例えば上がったのは、自分でUIを作ってみるというトレーニング。
自分たちよりも経験的に高くて成功しているサイトを参考に、
自分ならどうするかと考えてサイトを作るのも勉強になりそうですよね。
お題を考えて作る、というトレーニングを通してデザインの幅が広がりそうです。
(3)各自の「デザインするうえで大切なこと」の話を聞けた
日頃からチームのメンバーが、デザイナーとして持っている
「デザインするうえで大切なこと」について意見交換することができたことが大きかったです。
実際に「自分も同じ意見だ」という共通部分が見えてきたり、「そんなところまで気を遣っているんだ」など、各自が持っているデザインに対する思いなどを確認できる良い機会となったと感じました。
今回、デザイン研究課としては初めての読書会の試みとなりました。
次回はお互いの意見に対して自由にコメントできる雰囲気作りなど、
より有意義な読書会を作れるよう頑張っていきたいです!
デザインだけにとどまらず、読書をきっかけに同じチームの皆とコミュニケーションを図る、という体験は多くのきっかけを生んでくれるのではないでしょうか。
まずは短時間でも良いので、小さく始めてみるのも良いはずです。
ぜひおためしあれ。
しずおかオンライン中途採用社員も、積極募集中!
しずおかオンラインののスタッフとして、地域の魅力を伝える仕事です。
くわしくはこちら!


.png)

















